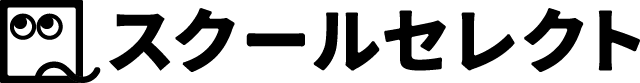PR
投稿日:2024年2月20日 | 更新日:2024年04月22日

「星や宇宙についての知識を増やしたい」
「天文や宇宙の知識を活かしたい」
そんなふうに思っている人がいるのではないでしょうか?
天文や宇宙の知識を活かすことができる検定があります。それが、今回ご紹介する「天文宇宙検定」です。
天文宇宙検定はあまり世の中には知られていませんが、今回はそんな天文宇宙検定の概要や試験、勉強方法などについて徹底解説します。
天文宇宙検定の活かし方次第では、就職や転職にもメリットがあるかもしれません。
是非、この記事を参考にしていただきチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
天文宇宙検定とは?

「そもそも天文宇宙検定って何?」と思っている人も多いのではないでしょうか?
まずは、その概要と魅力について深掘りしていきます。
天文宇宙検定とは?
天文宇宙検定とは、宇宙や天文学に関する知識や理解を評価するための資格試験です。
日本天文学会が主催、一般の人の宇宙に関する知識を広め、宇宙への興味を高めることを目的としています。
天文宇宙検定は1〜4級までのレベルが用意されており、どなたでも受験できます。
合格率に関しては、3級、4級は70%以上と高くなっており、2級になると50%前後、1級は難易度が高くなり、10%以下です。
天文宇宙検定の魅力は?
では、天文宇宙検定の魅力についても詳しく解説します。
宇宙の不思議を探求できる
天文宇宙検定は、宇宙に関する様々な知識を深めることができます。
銀河、星座、惑星、恒星の進化など、多くの宇宙の不思議を探究し、理解を深めることができます。
宇宙や星が好きな人にとっては、趣味が高じて資格も得ることができますので一石二鳥といえます。
賞賛と認定
各級の合格者には、証明書やバッジが授与されます。自分自身の宇宙に関する知識を認識できるだけでなく、証明書やバッジにより様々な場面で賞賛される可能性もあります。
1級に合格した場合は、天文宇宙検定を受ける人たちの間では有名になるのではないでしょうか?
もしかすると、それがきっかけで新たな仕事に繋がる可能性もあります。
自己投資と未来への貢献
天文宇宙検定を取得することは、自分自身の宇宙への好奇心をさらに高め、知識を深めることに繋がります。
さらに、そのような自己投資が新たな経験や仕事を生み出し、将来の科学者や宇宙飛行士、天文学者などを育てる一助になる可能性もあります。
次の世代に、宇宙への探究心をバトンタッチできる重要な役割を果たせるかもしれません。
天文宇宙検定がもたらすメリットとは?

では、天文宇宙検定を取得することでどんなメリットが得られるのでしょうか?
中には、就職や転職に活かせるのかが気になっている人も多いと思います。
結論からいうと、状況により異なります。その具体的な理由について解説します。
天文宇宙検定は就職・転職に有利なのか?
天文宇宙検定が就職や転職に有利かどうかは、残念ながら状況によります。
天文宇宙検定が有利なケースと、その理由について解説します。
科学・教育関連
天文宇宙検定は、宇宙の知識を深めることができ、教育機関で教師などをしている人、教師を目指している人にとっては有益と考えられます。
科学系の教師ならば、存分に知識を活かすことができます。科学館やプラネタリウムなどの施設運営や企画に携わる場合も恩恵を得られると考えられます。
サイエンスコミュニケーション関連
サイエンスコミュニケーションに携わる人にとっても有効な検定といえます。
ちなみにサイエンスコミュニケーションとは、自然科学や人文・社会学などの学術領域に携わる研究者と市民との間でなされる双方向的なコミュニケーションです。
一般の人に、宇宙などについて分かりやすく解説する科学ジャーナリストやサイエンスライターにとっては、仕事の幅が広がる可能性があります。
YouTubeなどで、自分自身で宇宙の魅力について発信する場合なども検定保持者であることで、牽引性を持つことができます。
研究・天文学者のアシスタント
検定取得後、天文学や宇宙科学の研究機関などに就職、転職する場合に自身の知識やスキルを証明する材料として役立つ可能性があります。
科学技術系企業
科学技術などを取り扱う企業の中には、宇宙に関連するプロジェクトなどもあります。そのような企業で働く場合にも、天文宇宙検定が役立つことがあります。
あくまでも、天文宇宙検定は知識を証明するものであり、就職や転職に活きるかは企業や組織次第であるといわざるを得ません。
まずは、自分自身の探究心や知識向上を目的に試験に臨み、副産物として就職や転職に役立つ可能性があるという程度に思っておくのが良いかもしれません。
天文宇宙検定を受験する前に知っておくこと

天文宇宙検定の魅力と活用方法について説明しましたが、ここからは天文宇宙検定の試験について詳しく解説します。
まずは、2023年5月に行われた検定の合格率について以下に記載します。
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
| 合格率(%) | 0 | 43.6 | 74.5 | 82.7 |
この結果から、1級の難易度の高さが非常に高いことが分かります。2級は、約50%前後と対策次第では合格できると考えられます。
まずは、3〜4級で力試しを行い試験に慣れることが良いかもしれません。
受験料
受験料に関しては、各級により金額が異なり、併願も可能で併願割引もあります。
| 1級 | 6,700円(税込) |
| 2級 | 6,200円(税込) |
| 3級 | 5,000円(税込) |
| 4級 | 4,400円(税込) |
| 2・3級併願(割引) | 10,000円(税込) |
| 3・4級併願(割引) | 8,460円(税込) |
| 2・3・4級併願(割引) | 14,000円(税込) |
申込み期間
天文宇宙検定は1年に2回あり、4月中旬、10月中旬が申込期間になることが多いようです。
試験日
試験日は、例年ですと5月下旬、11月中旬に行われており、第17回の試験は2024年6月9日です。合否については、7月上旬に発表されます。
試験時間
試験時間は、1〜4級50分です。開始前には10分間の説明もありますので、全て込みで1時間です。
かなりタイトな試験時間といえます。
出題形式
出題形式は、1〜4級すべてマークシート形式の4者択一方式です。
設問数は
| 1級 | 40問 |
| 2級 | 60問 |
| 3級 | 60問 |
| 4級 | 40問 |
天文宇宙検定各級の難易度と違いは?

上記でも記載しましたが、天文宇宙検定は1〜4級の4段階あり、それぞれで難易度が大きく異なります。
各級の難易度と出題傾向について解説します。
天文宇宙検定4級
4級は子供向けで、基本的な宇宙の知識を楽しみながら学ぶことができます。小学生が学ぶ程度の星座や宇宙、宇宙飛行士の活動などについて出題されます。
天文宇宙検定3級
3級に関しては、宇宙に関する基本的な知識を問う問題が多い傾向にあり、中学生で学ぶ天文学レベルです。
主に星座、惑星、月、太陽、宇宙望遠鏡などの基本的な知識に焦点を当てています。宇宙に関する基礎を学びたい人に適しています。
天文宇宙検定2級
2級は、天体の運動や恒星の進化、宇宙の歴史、天文学者が発見したこと、時事問題など、より高度な知識が必須です。より高度なレベルで知識を深めたい人に向いています。
天文宇宙検定1級
1級は、かなり高度な知識が必要で理工学大学レベルの天文知識が求められます。宇宙理論、宇宙の構造、宇宙の進化に関する知識、時事問題が問われます。
1級は、専門的な宇宙科学の分野に進みたい人に適しています。
試験範囲の傾向を把握する

各級の試験範囲の傾向についても深掘りしていきます。
4級
4級は、子供向けであり基本的な宇宙の知識を学ぶことができれば合格に近づきます。傾向は以下の通りです。
星座: 主要な星座の特徴と識別方法
宇宙飛行士: 宇宙飛行士の役割と宇宙での活動に関する理解
月の探索: 月の探査や月の特徴
太陽系の惑星: 太陽系内の主要な惑星に関する基本知識
3級
3級は、宇宙と天文学の基本概念の理解が合格の鍵です。傾向は以下の通りです。
星座: 主要な星座の特徴や位置、星座にまつわる物語など
惑星: 太陽系内の主要な惑星(水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星)に関する基本知識
月: 月の特徴や運動、観察
太陽: 太陽の構造や活動、日食と月食について
地球の自転と公転: 地球の自転と公転に関する基本知識
宇宙望遠鏡: 主要な宇宙望遠鏡や役割に関する知識
宇宙探査: 有名な宇宙探査に関する基本知識
2級
2級は、上記でも解説しましたが高度な知識が必要で3級に比べると難易度が上がります。傾向は以下の通りです。
天体の運動: 天体の自転、公転、楕円軌道に関する知識
恒星の進化: 恒星の生涯や進化段階、終末段階の知識
太陽系外の宇宙: 太陽系外の惑星、恒星、銀河に関する知識
宇宙望遠鏡と観測装置: 宇宙望遠鏡、観測装置や役割についての知識
天文学者: 天文学に貢献した天文学者の業績と貢献についての知識
1級
1級は、難易度からも分かるように相当高度な宇宙科学の知識が求められます。傾向は以下の通りです。
宇宙理論: 宇宙理論に関する知識
宇宙の構造: 銀河、星団、銀河団など宇宙の構造についての知識
宇宙進化: 宇宙の進化、ビッグバン理論、暗黒物質、暗黒エネルギーなど宇宙進化の知識
宇宙論: 宇宙論の基本原理、宇宙の拡大と加速に関する知識
クォーサーとダークマター: クォーサー、ダークマター、宇宙の謎についての知識。
宇宙背景放射線: 宇宙背景放射線と宇宙の起源に関する知識
天文宇宙検定の学習方法は?

天文宇宙検定の難易度と試験範囲について詳しく解説しましたが、学習方法についても詳しく説明します。
公式テキストや公式問題集など王道な学習方法からオンラインで学びを深める方法まで詳しく解説していきます。
公式テキストの反復学習が近道!?
様々な口コミや体験談から天文宇宙検定は、受験勉強同様に公式テキストを勉強する王道な勉強方法が近道と言われています。
公式テキストが発売されており、ご自身の受験する級のテキストを何度も読み返すことが重要です。
\「天文宇宙検定公式テキスト」での勉強がおすすめ!/
更に、公式テキストの各章には問題集があり理解度をチェックできます。この問題で不正解の箇所を重点的に復習し、何周もテキストを反復することで知識が定着します。
公式問題集で自信をつけるべし!
公式テキストで知識が定着した後、公式問題集に取り組むようにしましょう。
\「天文宇宙検定公式問題集」での勉強がおすすめ!/
公式問題集に関しても、何周も反復することが重要です。
受験した人の中には、テキストや問題集だけでなく、自分自身の不足している知識を得るために、物理や数学の基礎など関連する分野を中学レベルから再学習している人もいるようです。
YouTubeなどオンラインリソースを活用
公式テキストや問題集だけに留まらず、現在はYouTubeなどを利用して学習することもできます。
YouTubeには、天文宇宙検定に関する情報や試験対策をしているチャンネルもあります。
そのような動画を利用し、公式テキストと合わせて知識を深めるという方法もあります。
YouTubeなどで、ある程度の知識がついたならば、その後は公式テキストの問題と問題集を解くことをおすすめします。
問題を解かなければ知識が定着しづらいといえます。
上記を参考にしていただき、ご自身に合った勉強方法を選択してみてください。
試験対策のポイント

試験勉強について詳しく解説しましたが、試験対策のポイントもあります。時事問題も多く出題されますので、テキストとは別の対策が必要になります。
更に、試験当日の問題解答の時間配分なども合格の鍵となります。
関連図書を読む
公式テキストは、網羅的に細かく解説しているものの、中にはボリュームの関係で簡易的な説明になっていたり、難解な単語が解説されていなかったりします。
このような場合は、関連図書を読むことも重要です。
その際、科学雑誌「ニュートン」や「天文ガイド」などを読むことで難解な単語の理解が深まり、知識を定着させることができます。
時事問題対策にも、上記の雑誌は有効で役立ちます。
難解な単語などは、チャットGPTなどAIを使用して、理解を深めるのも良い手段であると考えられます。
問題解答時における時間配分のコツとは?
上記でも記載しましたが、天文宇宙検定の試験時間は、50分とかなり短いのが特徴です。
ですが、級が上がるごとに出題内容は高度なものになり、時間を効率よく使わなければ合格が厳しくなります。
そのことを踏まえると、「時間配分」が非常に重要です。受験経験者の口コミなどから判断すると、問題解答を2つのパターンに分けることが重要です。
•正解に自信があり見直しが必要ない問題
•正解に自信がなく見直しや時間をかける問題
この2つのパターンに分けることで、時間配分を明確にします。
一度すべての問題を問いた後、自信のない問題を今一度じっくり時間をかけて解くことが重要です。
このコツに加え、試験開始時に一度すべての問題を一度確認し、自信のない問題をあぶり出しておくことで、より効率よく時間を使用できます。
公式問題集を解く際にも、このやり方を癖づけるとよりスムーズに行えますので、是非試してみて下さい。
まとめ

今回は、天文宇宙検定の概要から受験に関わる情報、各級の難易度、出題範囲まで詳しく解説しました。
あまり知られていない検定ですが、天文や宇宙に関わる仕事に有利な場合があり、就職や転職のメリットになる可能性もあります。
4級から受験すればハードルも低いので、天文や宇宙に興味がある人は、自分自身の知識を深めるという目的で受験してみてはいかがでしょうか?
今回の記事を、少しでも参考にしていただければ幸いです。